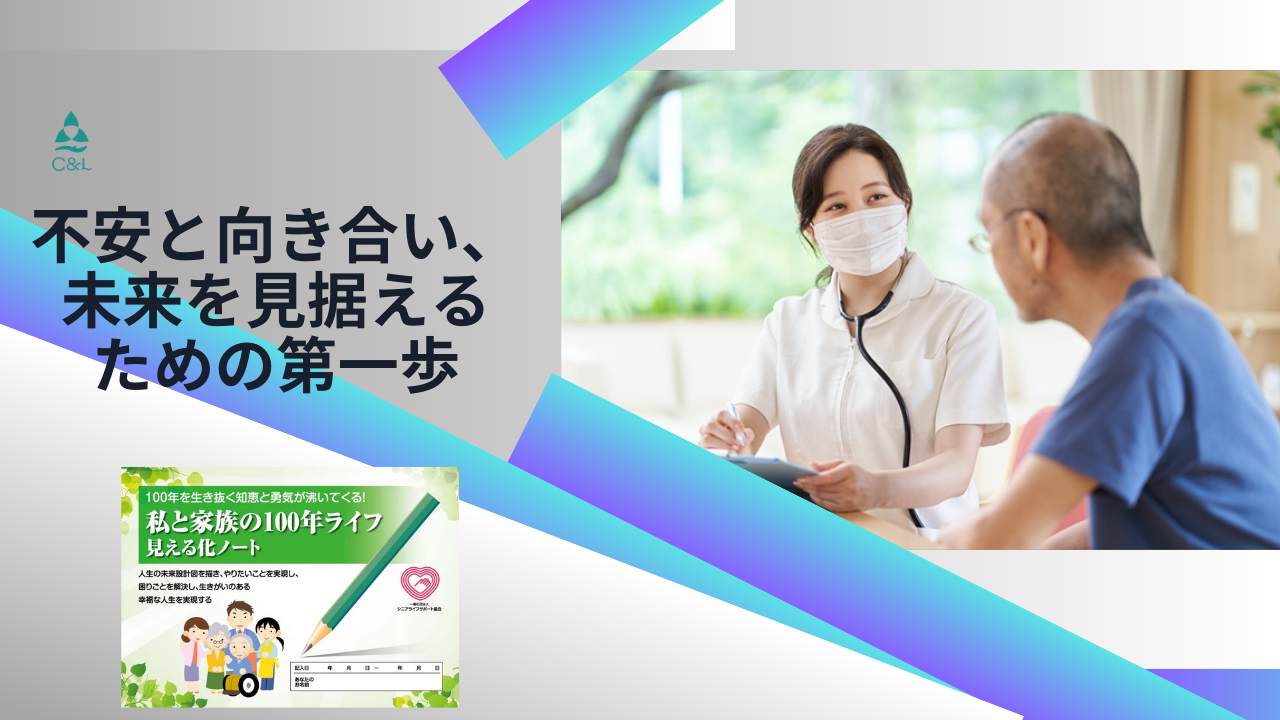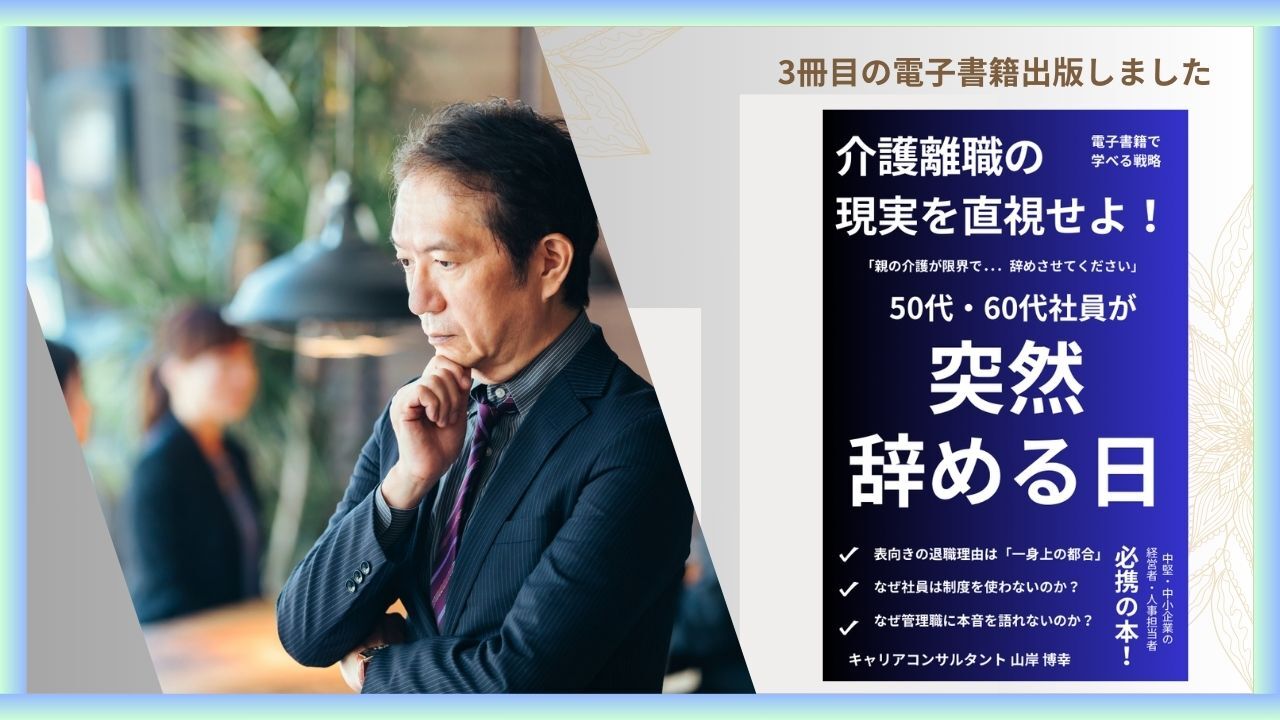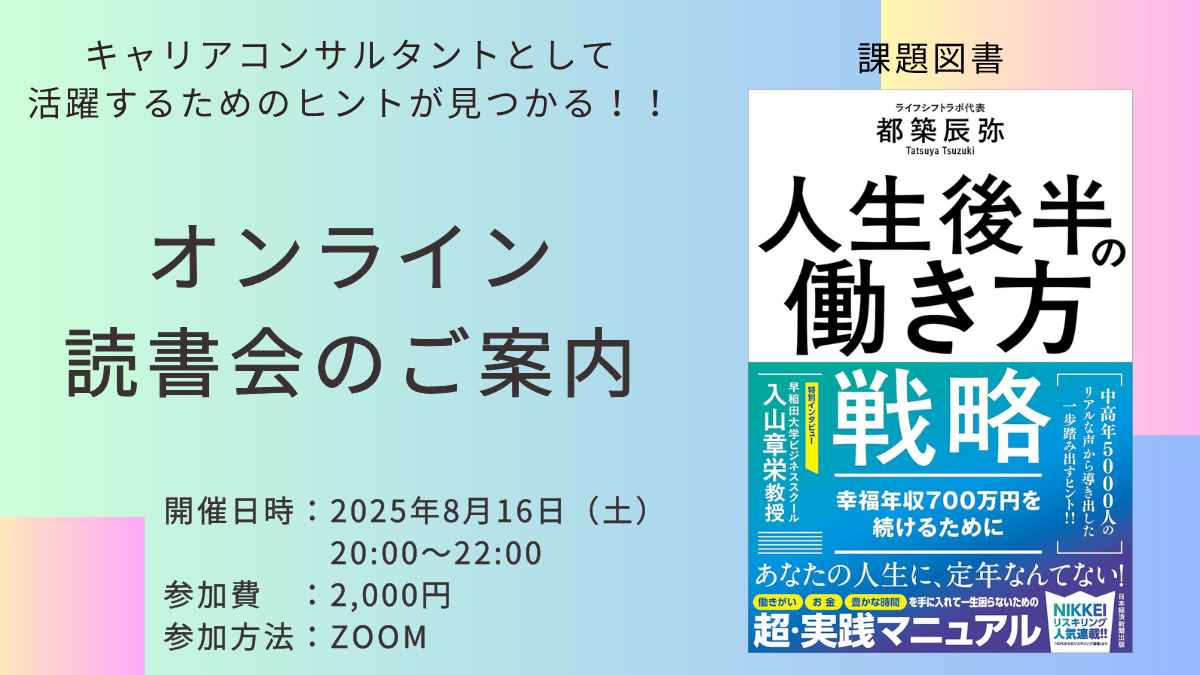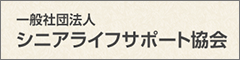介護のお金、見て見ぬフリはもう終わり。家族を守る「経済的準備」を始めよう

はじめに
前回の【準備編①】では、後悔しないための「施設の見抜き方」と「家族会議の進め方」について解説しました。
しかし、どんなに理想的な介護プランを描いても、その実現可能性を左右するのが「お金」の問題です。
そこで今回は【準備編②】として、多くの人が目を背けがちですが、避けては通れない「介護の経済的準備」に焦点を当てます。在宅介護と施設介護のリアルな費用比較から、知っているだけで数十万円単位の差がつく公的なセーフティネットまで、具体的な数字を交えながら、家族を経済的な不安から守るための知識を徹底的に解説します。
経済的な全体像の把握
介護費用は、家族にとって大きなストレス源であり、選択肢を狭める要因にもなります。
まずは、在宅介護と施設介護、それぞれの費用感を具体的に把握することが不可欠です。
ここでは「費用」という抽象的な概念を具体的な数字に落とし込み、家族が予算計画を立てる上での現実的な土台を提供します。
要介護3のモデルケースで、月額費用の目安を比較してみましょう。
-
在宅介護の場合
-
介護サービス費(自己負担分):約37,000円
-
その他雑費(医療費、日用品等):約20,000円
-
合計(月額目安):約57,000円 + 既存の生活費(家賃や光熱費など)
-
初期費用として、住宅改修費などがかかる場合があります。
-
-
特別養護老人ホーム(特養)の場合
-
介護サービス費は施設サービス費に含まれます。
-
居住費・食費・光熱費など:約80,000円
-
その他雑費(医療費、日用品等):約20,000円
-
合計(月額目安):約138,000円
-
初期費用は、基本的にはかかりません。
-
-
介護付き有料老人ホームの場合
-
介護サービス費は月額利用料に含まれます。
-
居住費・食費・光熱費など:約180,000円
-
その他雑費(医療費、日用品等):約20,000円
-
合計(月額目安):約297,000円
-
初期費用として、数十万円から数千万円かかる場合があります。
-
(注) 上記はあくまで一般的なモデルケースです。
費用は地域、所得、利用サービス、施設のグレードによって大きく変動します 。特に民間施設では、高額な入居一時金が必要な場合があります 。
在宅介護の費用は、介護保険の自己負担分に加えて、既存の家賃や光熱費などがかかります。
経済的なセーフティネット:高額介護サービス費制度
この制度は、介護における経済的負担を軽減するための重要な仕組みです。簡単に言えば、1ヶ月の介護保険サービスの自己負担額に上限を設け、上限を超えた分が払い戻される制度です 。
-
対象となる費用: 訪問介護、デイサービス、施設サービス費など、ほとんどの介護保険サービスが対象です 。
-
対象とならない費用: 施設での居住費や食費、おむつ代などの日用品費、福祉用具の購入費、住宅改修費などは対象外です 。これは非常に重要なポイントで、予算計画を立てる際に混同しないよう注意が必要です。
-
自己負担上限額: 上限額は、世帯の所得によって異なります。例えば、住民税非課税世帯では月額24,600円、一般的な所得の世帯(課税世帯)では月額44,400円が上限となります 。
-
手続き: 初めて対象となった際に市区町村から申請書が送付され、一度申請すれば、その後は自動的に計算され、指定口座に振り込まれるのが一般的です 。
この制度を正しく理解し活用することで、介護費用の見通しが立てやすくなり、経済的な不安を大幅に軽減することができます。
「準備編」は今回で終了です。
次回からは【計画編】として、「在宅か施設か」という二者択一ではない、より柔軟で戦略的な「段階的介護プラン」の立て方を解説します。
日本の介護保険サービスを最大限に活用し、親の状態に合わせて最適なサポートを組み立てる方法をご紹介します。
そして、家族会議時のコミュニケーションのツールとしてとても有効なのが、「私と家族の100年ライフ 見える化ノート」です。
まずは体験ワークショップにご参加頂き、どのようなものなのか?どのようなことをするのかを知って頂ければと思います。
「私と家族の100年ライフ 見える化ノート 体験ワークショップ」お申込みはこちらから