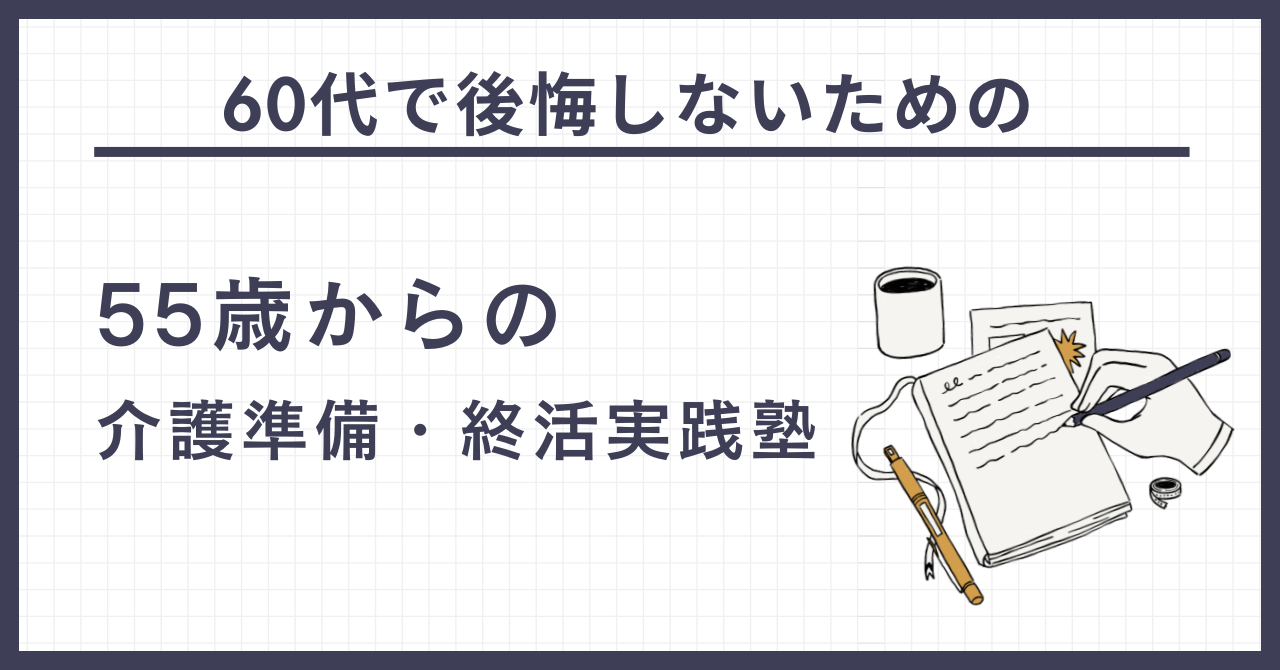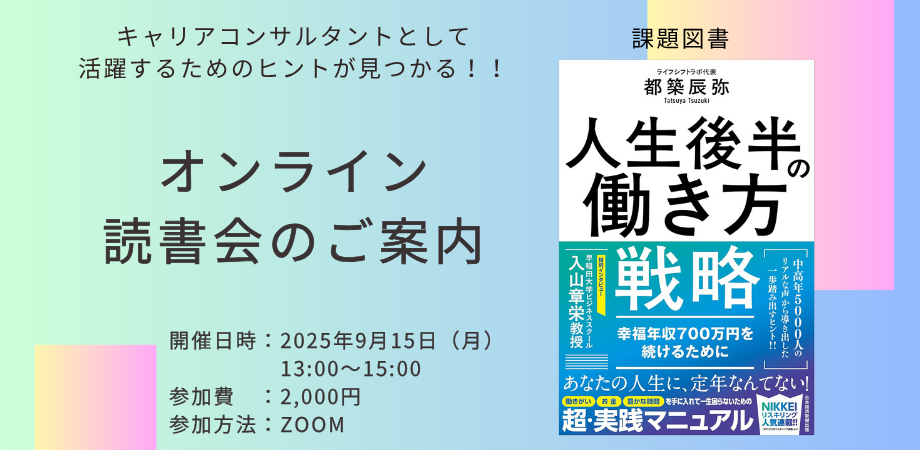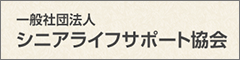「もう、ひとりで抱えないで」―50代、60代からのキャリアと介護、”最悪の事態”を乗り越えた私だからこそ、伝えられることがある

はじめに:なぜ私は、この事業に人生を懸けているのか
いつも私の発信をご覧いただき、ありがとうございます。キャリア&ライフプラントータルサポート代表の山岸 博幸です。
今回は、改めて自己紹介をさせていただくとともに、なぜ私が「キャリア」「介護」「生活設計」という3つのテーマを統合してサポートするという、他に類を見ない事業を立ち上げるに至ったのか。
その原点にある想いを、改めてお伝えしたく、この記事をかいております。
すでにご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、私の原点は、キャリアコンサルタントでありながら、自身の親の介護で心身ともに追い詰められた、壮絶な経験にあります。
そして、ある日、尊敬してやまない親を前に、心の内でこう叫んでしまいました。
『早く、この状況が終わってほしい...。』
『いつまで、生きているのかな...?』
『自分のキャリアも終わりかな?(詰んだかな?)』
『全く何で自分が犠牲にならなきゃいけないんだ?』
『全くもう...。疲れたなあ!!』
親を想う気持ちとは裏腹に、どうしようもないほどの負担感から、そんなことを願ってしまった自分。
その事実に、私は深い自己嫌悪に陥りました。
しかし、この経験こそが、私の人生を大きく変え、現在の事業を立ち上げる原点となったのです。
これは、特別な誰かの話ではありません。50代、60代という人生の岐路に立つ多くの人が直面する、しかし、あまりにも語られることの少ない、現実の物語です。
そして、もしあなたが今、かつての私と同じように孤独と不安の中で立ち尽くしているのなら、この記事を最後まで読んでみてください。
私がどうやってその暗闇を乗り越えたのか?
そして、その経験から生まれた「キャリア」「介護」「生活設計」を一体で支えるという答えが、あなたの明日を照らす一筋の光になるかもしれないからです。
順風満帆からの転落。二度の会社破綻と介護離職の危機が、私に教えてくれたこと
私のキャリアの出発点は、保険業界でした。約20年間にわたり、生命保険会社および生損保代理店で営業管理職を務め、ありがたいことに多くの表彰をいただくなど、仕事は順調そのものでした 。
当時は、「このまま会社員として勤め上げ、安定した人生を送るのだろう」と漠然と考えていました。
しかし、その「当たり前」は、ある日突然、崩れ去ります。
二度にわたる、勤務先の経営破綻と吸収合併です 。
昨日まで信じていた「会社」という存在がいかに脆いものであるか、そして、会社に依存したキャリアがいかに危険であるかを、骨身に染みて思い知らされました。
この強烈な経験が、「自分のキャリアは自分で創り上げなければならない」という意識を私に植え付け、キャリアコンサルタントへの転身を決意させたのです 。
新たな道へ踏み出し、まさにこれからという時でした。私を第二の、そしてさらに深刻な危機が襲います。親の介護問題です。
キャリアの再構築という大きな課題に取り組む中で、突如として降りかかってきた親の介護。
仕事の準備、新しい知識の習得、人脈作り。やらなければならないことは山積みです。
しかし、それと同時に、病院への付き添い、役所での手続き、日々の身の回りの世話といった介護のタスクが、容赦なく私の時間を奪っていきました。
キャリアへの焦り
介護の終わりが見えないことへの不安
経済的な負担
精神的な疲労
肉体的な疲労
これらが複雑に絡み合い、私の心と体を蝕んでいきました。
まさに、キャリアと介護という二つの危機が同時に押し寄せる「パーフェクトストーム」の只中にいたのです。
この経験を通して、私は一つの確信を得ました。
それは、「キャリアの問題」と「介護・生活の問題」は、決して切り離して考えることはできない、ということです。
キャリアプランを立てても、介護という予期せぬ事態で頓挫してしまう。
介護に専念しようとすれば、自身のキャリアが途絶え、経済的な基盤が揺らいでしまう。
この二つは、常に連動しているのです。この気づきこそが、後に「キャリア&ライフプラントータルサポート」という、他に類を見ない統合的支援サービスの根幹を成すことになります。
50代、60代を襲う「3つの崖」。なぜ、キャリア・介護・生活設計は”個別”に解決できないのか
私の経験は、決して特別なものではありません。むしろ、50代、60代という年代に差し掛かった多くの人が直面する、構造的な問題なのです。
私はこの問題を、「3つの崖」と呼んでいます。
-
キャリアの崖
会社員としてのキャリアが頭打ちになり、役職定年や早期退職といった現実に直面する時期です。これまでの経験を活かして転職や再就職を目指すのか、あるいは副業や独立といった新たな働き方に舵を切るのか?。
人生100年時代を見据え、「第二のキャリア」の構築を迫られる、まさに崖っぷちの状況です。
-
介護の崖
親が病気で倒れるなど、ある日突然、介護が始まる崖です。
何の前触れもなく、昨日までの日常が一変します。
誰に相談すればいいのか、何から手をつければいいのかも分からず、混乱と不安の中で時間だけが過ぎていく 。
仕事との両立に行き詰まり、「介護離職」という選択肢が頭をよぎる、非常に危険な崖です。
-
生活設計の崖
親の介護を通じて、自分自身の老後や将来設計について、現実問題として突きつけられる崖です。
親の介護費用は誰が負担するのか。自分たちの老後資金は大丈夫か。
もし自分に万一のことがあったら、障害を持つ子どもの将来はどうなるのか 。これまで漠然と先延ばしにしてきた「人生全体の設計図」の再構築を迫られます。
多くの方が陥りがちなのが、これらの崖を「別々の問題」として捉え、個別に対処しようとすることです。
キャリアのことはキャリアコンサルタントに、介護のことはケアマネージャーに、お金のことはファイナンシャルプランナーに...。
しかし、それでは根本的な解決には至りません。
なぜなら、この3つの崖は、地下で固い岩盤のようにつながっているからです。
例えば、介護のために今の仕事を辞める(介護の崖から飛び降りる)という決断は、あなた自身のキャリアを断絶させ(キャリアの崖から突き落とされ)、老後の資金計画を根本から覆します(生活設計の崖をも崩壊させてしまいます)。
一つの崖への対処が、他の崖をより険しくしてしまう。
この相互関係を理解せずして、真の安心は手に入らないのです。
だからこそ、これら3つの課題を一つのテーブルに乗せ、全体を俯瞰しながら最適解を導き出す「統合的アプローチ」が絶対に必要となるのです。
「もう誰も、私と同じ道を歩ませない」ワンストップ支援に込めた誓い
「キャリア」「介護」「生活設計」。この3つの崖の間で身動きが取れなくなり、孤独と絶望の淵をさまよった私だからこそ、強く心に誓ったことがあります。
「もう二度と、誰も私と同じ道を歩ませない」
この誓いを形にしたのが、私が運営する「キャリア&ライフプラントータルサポート」です。その最大の特徴は、あなたが抱える「キャリア」「介護」「生活設計」の悩みを、一つの窓口でまとめてサポートする「ワンストップ支援」にあります 。
私が目指すのは、単なるアドバイザーではありません。
あなたの人生というプロジェクト全体をマネジメントする、信頼できる「伴走者」です。
突然始まる介護への戸惑いや不安に寄り添い、約5,200名のキャリア相談実績を基にあなたにとって最適な仕事と介護の両立プランを一緒に考えます 。
そして、介護には法律、不動産、相続など、様々な専門知識が必要となる場面が必ず訪れます。私自身が一人で奔走し、苦労した経験から、各分野の専門家との強固なネットワークを構築しました。
司法書士、行政書士、税理士、弁護士、不用品買取業者、不用品処分業者、不動産業者といったプロフェッショナルたちと連携し、あなたが必要とする専門知識を、必要なタイミングで的確にお届けする 。
それぞれの専門家を、自分自身の相談内容を解決できる専門家、直面の課題を正しく、しかも迅速に解決できる本当のプロの専門家を見つけることは実際にはそう簡単なことではありません。
私に相談するだけで、問題解決に必要なチームが、あなたの後ろには控えているのです。
この事業の目的は、ただ問題を解決することだけではありません。
私たちのサービスを通じて、
「介護の悩みを安心に」変えること
「介護者も被介護者も笑顔の終活」を実現すること
「人生100年時代を活き活きと生き、働くこと」を実現すること
です。
それが、私の掲げる最大のミッションです。
先の見えない不安を、未来への具体的な計画へと変えていく。そのための羅針盤となることが、私の存在意義なのです。
私たちが、”一緒に”解決できること:サービス内容のご案内
キャリア&ライフプラントータルサポートでは、あなたが直面する課題に応じて、具体的で実践的なサポートを提供します。これまで約5,200名のキャリア相談に応じてきた経験 を土台に、一人ひとりの状況に合わせたオーダーメイドの支援を行います。
個人のお客様へ
前述の「3つの崖」を乗り越えるためのトータルサポートを提供します。
-
キャリア支援
-
こんなお悩みを解決します:
-
「今の仕事を続けながら介護できるだろうか?」
-
「この歳で、新しい働き方は見つかるのか?」
-
-
具体的なサポート内容:
-
介護と仕事を両立するためのキャリアカウンセリング
-
ミドルシニアの転職・再就職支援
-
複業・独立に向けた準備コンサルティング
-
-
-
介護支援
-
こんなお悩みを解決します:
-
「親が倒れた!まず何をすればいい?」
-
「誰に、どこに相談すればいいか分からない...。」
-
-
具体的なサポート内容:
-
突然の介護発生時の初期対応アドバイス
-
複雑な行政手続きのナビゲーション
-
弁護士、司法書士など専門家ネットワークへの連携
-
-
-
生活設計
-
こんなお悩みを解決します:
-
介護施設の選び方のポイントや費用について
-
「自分に万一のことがあったら、この子はどうなる?」
(障がいを持つお子様) -
「老後の資金や生活が漠然と不安...。」
-
-
具体的なサポート内容:
-
障がいを持つお子様の将来設計サポート
-
適切な介護施設のご紹介
-
「人生100年時代」を見据えたライフプランニング
-
「ラブポチ信託」(ペット信託)に関するご相談
-
-
ペットを飼われているお客様へ
50代以上の方にとって、ペットはかけがえのない家族の一員です。
-
「自分が入院したら、この子はどうなるのだろう」「将来の介護が不安で、新しいペットを迎えるのをためらってしまう」といった声にお応えします 。
-
あなたに万一のことがあっても、大切なペットが安心して生涯を暮らせるように備えるためのペット信託「ラブポチ信託」の普及推進も行っています 。
法人(経営者・人事担当者)のお客様へ
社員の介護離職は、今や企業にとって無視できない経営課題です。
経験豊富な中核社員を失うことは、企業にとって計り知れない損失となります。
-
介護離職を未然に防ぐための、法人向けコンサルティングを提供しています 。
-
具体的なサポート内容:
-
社員向けの介護セミナーの開催
-
社内に専門の相談窓口を設置し、専門家が定期的にカウンセリングを行う支援
-
「安心」への第一歩は、話すことから。まずはお気軽にご相談ください
ここまで長い文章を読んでいただき、本当にありがとうございました。
もし、あなたが今、キャリア、介護、生活設計のいずれか、あるいはそのすべてに悩みを抱えているのなら、どうか一人で抱え込まないでください。
かつての私がそうであったように、問題が複雑に絡み合っている時ほど、人は思考の迷路にはまり込み、身動きが取れなくなってしまいます。そんな時、最も大切なのは、信頼できる誰かに「話す」ことです。
あなたの状況を整理し、課題を一つひとつ可視化し、解決への道筋を一緒に見つけ出す。そのための最初のステップとして、まずは私にお話をお聞かせください。
初回のご相談は、あなたの不安を吐き出すための時間です。無理な勧誘などは一切ありませんので、ご安心ください。
「安心」への第一歩は、話すことから始まります。あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。
事業者情報
屋号 キャリア&ライフプラントータルサポート
代表 山岸 博幸
所在地 〒331-0814 埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目423番地
さくらヴィレッジ707号室
電話番号 090-3903-8408
受付時間 9:00〜19:00(土・日・祝日も営業しております)
ウェブサイト https://career-life.org/
この記事の動画はこちらから
つらい介護を一人で悩まず、乗る超えるためのコミュニティにあなたも参加しませんか?
▼オンラインサロン無料説明会の詳細・お申込みはこちらから
①11月06日 (木) 20:00〜 21:00
https://kaigosalon.peatix.com/
②11月26日 (水) 20:00〜 21:00
https://kaigosalon2.peatix.com/