「まだ早い」が招く後悔。沈黙がもたらす本当の代償とは?
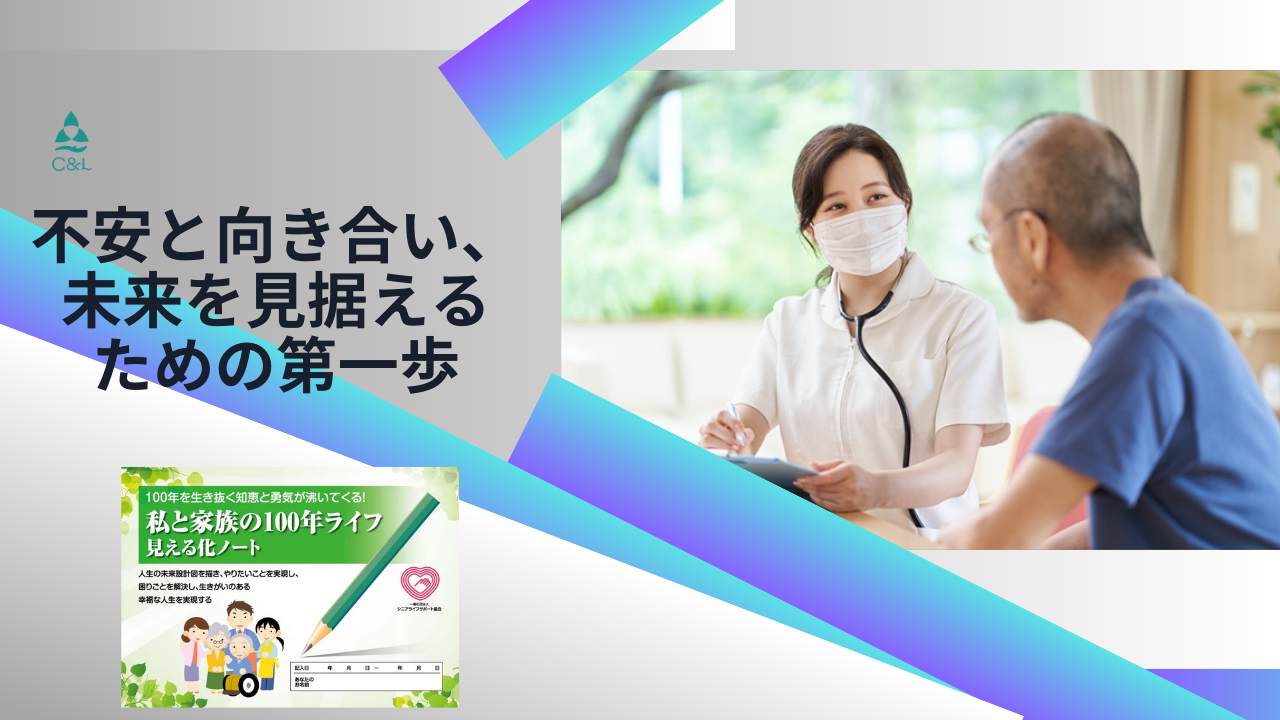
前回、多くの人が親との「これからの話」を先延ばしにしがち、という問題提起をしました。では、なぜ「今」話すことがそれほどまでに重要なのでしょうか。
その答えは、先延ばしがもたらす「後悔」の深刻さにあります。
沈黙が破られるのは、多くの場合、親が病で倒れたり、認知症と診断されたりといった、突然の「危機」が訪れたときです。その瞬間、家族は極度のストレスと混乱の中で、親の真の意向を知らないまま、重大な決断を次々と迫られます。
その結果生まれるのが、「もっと早く、きちんと話しておけばよかった」という、深く、そして長く続く後悔です。
ある人は、
医療機器に繋がれた母の姿を前に「家に帰りたい」という最期の願いを叶えられなかった無念を、何年も引きずっています 。
またある人は、本人の意思が分からないまま延命治療を選択してしまったことへの苦悩を抱え続けています 。
それは、「本当にこれで良かったのだろうか」という、答えの出ない問いとの、終わりのない戦いです。
この「危機主導」の意思決定は、家族関係そのものにも深刻なダメージを与えます。事前に役割分担や費用について話し合わなかった兄弟姉妹が、お金や介護の負担をめぐって激しく対立し、関係が修復不可能になるケース(いわゆる「家族崩壊」)も決して少なくありません 。
このように、対話の先延ばしは、単なる準備不足以上のものを意味します。それは、家族というシステム全体が「問題を避けることで、かろうじて平穏を保つ」という、不健全で脆い均衡状態に陥っていることの現れなのです。
次回は、私たちをこのような状態に陥らせる、対話を阻む「感情の壁」について、さらに深く掘り下げていきます。
親との話し合うきっかけ作りに是非ご活用ください。
まずはご自身が体験頂いた後に、親御様、ご兄弟でご一緒に参加頂く形が一番良いと感じています。
「私と家族の100年ライフ見える化ノート 体験ワークショップ」のお申込みはこちらから




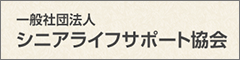
投稿されたコメントはありません