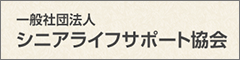「知ってる」と「できてる」は大違い。介護・終活準備を"完了"させる4つの具体的な成果物
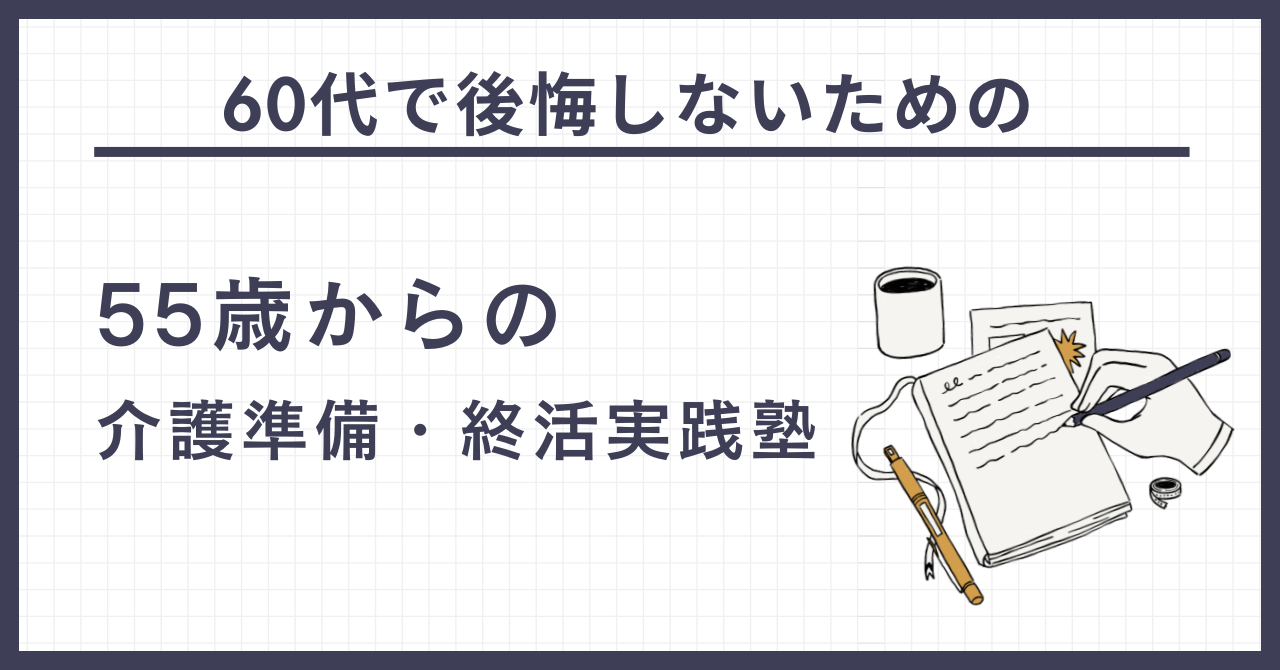
「介護や終活のセミナーに参加して、勉強になった」
「本を読んで、知識はついた気がする」
そう感じた後、あなたは具体的な行動に移せているでしょうか?
公的機関のセミナーや無料の勉強会も貴重な情報源です 。
しかし、多くの場合、一方的な情報提供だけで終わり 、個別の実践的なサポートはありません 。
その結果、「知ってはいるけれど、何もできていない」という状態が続き、いざという時に「あの時やっておけば...」と後悔することになります。
「知っている」ことと、「できている(=準備が完了している)」ことの間には、大きな溝があります。
その溝を埋めるために必要なのは、曖昧な知識ではなく、「形になった成果物」です 。
「55歳からの介護・終活実践塾」は、単なる「講座」ではなく、4ヶ月かけて具体的な成果を"形"にする「実践塾」です 。
このプログラムを通じて、あなたは以下の4つの具体的な成果物を手に入れることができます。
これこそが、あなたの「後回し」を卒業させ、将来の不安を安心に変える"証"となります。
1. エンディングノート作成サポート
自分の人生の価値観や希望を整理し、もしもの時に大切な人に伝えたい思いを形にします 。
これは、家族があなたの意思を尊重するための「道しるべ」となります。
2. 私と家族の100年ライフ見える化ノートの作成サポート
第6回でも触れた、お金の不安を解消する鍵です。親の価値観や希望を理解したうえで、将来の収支や、介護にかかる費用を具体的に可視化し、安心できる経済計画を立てられます 。
また、親や兄弟との話し合いを進めるうえでも非常に役立つノートです。
3. 親子合意リスト
「どう話せばいいかわからない」という壁を乗り越えた証です。家族間の話し合いのポイントをまとめ、お互いの理解と合意を形にします 。
介護計画を具体化するうえで、非常に重要なステップであり資料です。
4. 医療・介護意思整理シート
「その時」が来た時に、家族が決断に迷わないように。
もしもの時の医療や介護の希望を具体的に整理し、家族の判断の助けになるシートです 。
延命治療をどうするのか?親は尊厳死についてどのように考えているか?を事前に知り、親子間、兄弟間でしっかり話し合っておくことで、介護のストレスが軽減され、その後相続が発生したあとも良好な家族関係が維持できます。
これらの成果物を、専門家の伴走サポート(個別面談 やLINE無制限相談 など)を受けながら、4ヶ月で着実に完成させていく。
それが、本講座が目指すゴールです。
「勉強になった」で終わるのは、もうやめにしませんか?
まずは90分の無料説明会で、あなたの不安を「具体的な成果物」に変えるための最初の一歩を一緒にスタートしましょう!!
▼この記事の解説動画はこちらから
https://youtu.be/Y7uBqRLouPA
▼90分無料説明会へのご参加はこちらから
1.11月14日(金)20:00~
https://peatix.com/event/4637530
2.11月22日(土)20:00~
https://kaigojissen5.peatix.com/
3.11月23日(日)20:00~
https://kaigojissen6.peatix.com/
4.11月29日(土)20:00~
https://kaigojissen7.peatix.com/